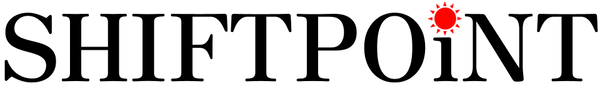昨今、モノやサービスの値段がうなぎ上りに上昇しています。特に、日常品に関してはかなり痛いですね。。大体、食料品・日常品を購入するときは、頭の中でざっくり計算をしながらカゴの中に入れていき、最終レジで精算するのですが、今まで感覚的に2,000円くらいで買えていたのが、2,000円後半、もしくは3,000円台に乗っかかるようになりました(イオンでは、レジゴーというアプリを使い、カゴに入れる都度バーコードを読みながらカゴに入れる都度、合計が表示されるのですごく便利です。かつ精算もQRコード1発読みですぐに処理ができ、レジに並ばないのでストレスフリー。)
「え?!重複しているのかな?」と思い、ざっとアプリをスクロールして確認をするのですが、間違ってはおりません。単純に、各商品が全て(微増)値上がりをしているので、10円単位もしくは100円近くの値上がりが重なると一気にこのような合計額になります。これは、本当に”塵も積もれば山となる” だな、と思いました。
今まではニュース等で「カップラーメンが15円、カレー粉が20円値上がりしました!」と報道されても「仕方ないよそれぐらい」と思っておりましたが、買物カゴにそれらが重なると、やはりインパクトは大きいと再認識しました。
「なんだかなぁ・・」と思いながらレジに行くのですが、そもそもインフレ自体は国にとっては良いことだと思います。ただし、急激なインフルではなく、時間をかけて微増していく、すなわちそれは(国として)成長している証だと僕は思っております。
周辺国アジア周辺国含め世界を見ると、そのような状態で成長率というのが上がっているのですが、日本は失われた30年と言われてるように、90年代初頭にバブルがはじけてからは成長と言うものがなくなりました。
特に痛かったのが80年代後半まで日本がイケイケだった電子機器業界、米国は「プラザ合意」や「日米半導体協定」などで日本の成長の芽を摘み、日本をバブル崩壊に追いやりました。
そのような政治的敗北が続き、この国は成長という事をできなくなる環境に陥り、その影響で「変わらない」という道を選びました。その後、その路線が今まで連綿し、30年という時間をかけて現在に至ります。
しかし、それは日本国内だけの話。他国はお構いなしに成長を続け、気がつくと日本国内には外国人が溢れている、インバウンド祭りです。そこでは、今まで培った価値あるモノが安い値段で海外へ売られる始末。
一方で、世界標準に合わせなければ生き残りが難しくなってきているので、各社値上げをする。でも、国民は「なんで値上げするんだ!」と声高々に叫びます。
このような構図ではないのでしょうか。レジゴーのQRコードをかざし、合計金額が表示される数字を見ながら、ぼんやりとそのような事を考えながらお店を後にします。
話を戻すと、急激なインフラと言うのは本当は防げていた事なのです。要は、この30年間にかけて微増して右肩上がりで上がっていかなければいけなかった「差異」だと思います。結局、その部分がなくずっとデフレになりすぎて(安けりゃ良い)と言うマインドが30年間という時間をかけて、日本人のマインドに植え付けられたので値上げに対しての抵抗感が各所で垣間見れるのです。
何でも「くれくれ星人」の比率が多い団塊世代の人たちは見ているとなんだか悲しくなる部分もあります。先日知り合いのカフェの店主とお話をしていて、その店主はあるお客にぼやいておりました。年齢は60代前後のおばさんでお店に入ってくるやいなや、「どうしてケーキがこんなに高いの?なんでこんなに高くなったの?」と、若干食ってかかってきたような言い草で言われたそうです。昨今の原料費の値上がりをするに提供側としては、値上げは至極当然であり、逆にそれをしないと存続すらできません。
しかし、サービスを受け取る側はそんなことを知った事ではなく、自分さえ良ければ良いと言う考えです。で、その店長はその女性の方に「この先にコンビニがあります。そこにお求めのお値段のケーキがあるので、そちらでどうぞ」と言って追い返したことがあったそうです。
まぁ、そりゃそうですよね。
一方で、やはり良いサービス良い商品に対しては、それだけの価値が生産者側によって体現されているので、それに対して価値を感じる人は、その対価を喜んで支払う習慣がなければいけないと思います。これは肌感覚なのですが、見ているとやはり富裕層の方々はその点をわかっているので、さっとお金払いがよく印象があります。だからこの富裕層のレイヤーに行けたのだなと思います。
わかります、「無い袖は振れない」事も。
ただ、多くの人には「貧すれば鈍する」より「窮すれば通ず」の方に向かってもらいたいです。