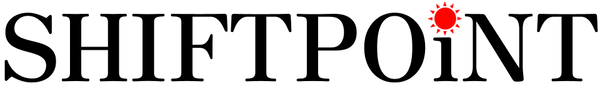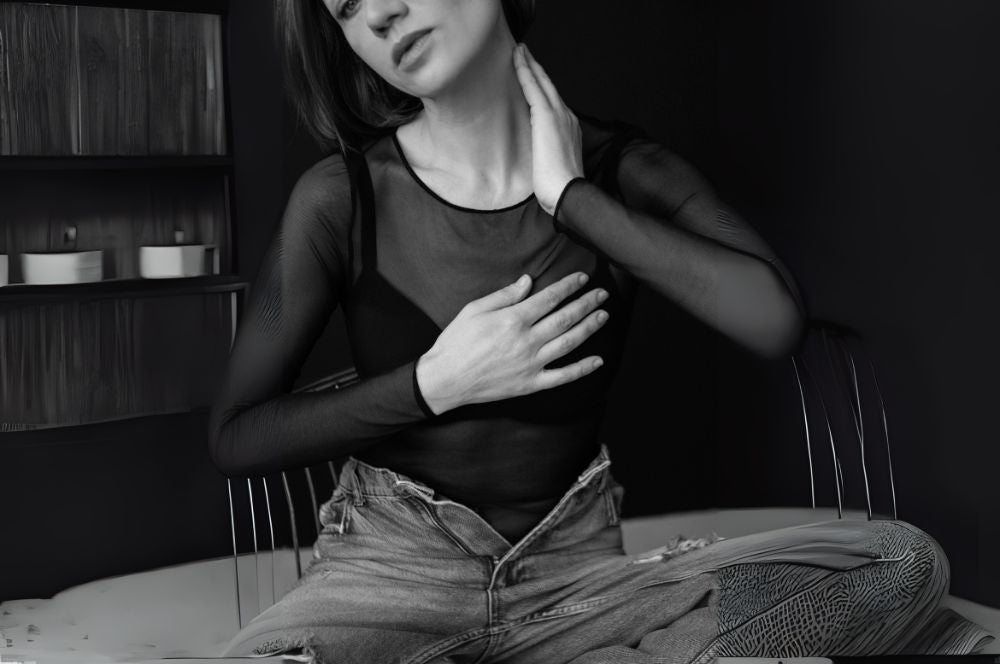◆ 「違和感」とは何か
先日、「違和感」と「先入観」の違いについてブログに書きましたが、最近も日常生活や仕事の中で改めて考えさせられる出来事がありました。酷い“サル真似”を受けることもあれば、普段のやり取りの中で妙な引っ掛かりを覚えることもあります。結局のところ、僕たちの生活は「違和感」と常に隣り合わせなのだと感じています。
◆ 辞書的な定義と僕の感覚
辞書では、違和感とは
「自身の感覚や認識と現実の状況が一致しないときに生じる心理的な不快感」
とされています。確かにその通りなのですが、僕にとっての違和感はもう少し実践的なものです。それはこれまで積み重ねてきた経験から導かれる“直感の結晶”。理屈や理論を一瞬で飛び越え、まだ言葉にならない段階で、近い未来に起こり得ることを知らせてくれるサインのような存在です。
イメージで言えば、ピンボケの映像がふっと浮かび上がってくる感覚に近い。言語化できる前に、体が先に反応しているのだと思います。
◆ 微弱なサインを無視しない
違和感には強弱があります。微弱なサインのときもあれば、胸を突き上げるような大きな違和感として現れるときもある。重要なのは、微弱なときにそれを受け止められるかどうかです。小さな引っ掛かりを「気のせいだ」と片付けてしまうと、やがてそれは関係の歪みやトラブルとして大きく表面化してしまう。僕自身、過去にそれを痛感してきました。
◆ サル真似と違和感
今回の「サル真似」に関しても同じです。もし1月の時点で法的な処置をしていれば、公的な記録を残すことができ、今後SNSなどで堂々と発信するための土台になっていたはずです。そう考えると、あの時の“微弱な違和感”を見過ごしたのは失敗でした。
そして今もなお、当該人物がSNSでキラキラした発信を続ける一方で、裏では人を貶めるような行動をしている。その姿を見ると、やはり「違和感しかない」と強く感じざるを得ません。言葉や態度が一見整っていても、本質は隠せないのだと痛感しています。
◆ 日常生活での違和感
日常生活でも同じです。小さな違和感は放っておけば必ずどこかで現実化する。だからこそ、「あれ?」と感じたら立ち止まって確認することが大切です。人間関係でも、ビジネスでも、家庭内でも。違和感を軽視すると、後々大きな摩擦や不信感につながります。
逆に言えば、違和感は未来を守るサインです。違和感を拾い上げて深掘りする習慣があれば、トラブルを未然に防ぐことができる。僕は経験を重ねるごとに、その確信を強めています。
◆ 「違和感」は、ほぼ正しい、と思う。
違和感は、未来を守るための直感です。理屈で説明できない段階でも、それを感じ取れるかどうかが人生の舵を大きく変える。僕は今後も、このサインに耳を傾け続けたいと思います。そして、違和感の先に見えてくるのは、「本物」と「偽物」を見極める力だと思っています。
「自分軸」を持って歩んでいく。
これが、僕が今回の経験から得た一番大きな学びでした。