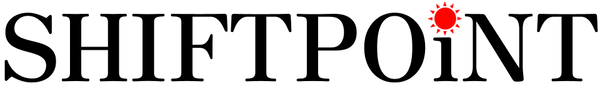◆ 今回のブログ発信をした理由
先日、Own Media 論( https://shiftpoint.jp/blogs/entry/2025-0805 )でも伝えたように、ある当該者(社)からの真似が余りにも目に付くので、キチンとエビデンスを残しておこうと思ったのが経緯です。
先日、たまたま、知り合いからの指摘があり、当該者のウェブサイトを見ると、今まで無かったブログのページが、2025年9月から記載されてました。内容を見ると、カビなしコーヒーを作った経緯を書いており、出だしから当方の言い回しをコピペした感が否めませんでした。
さらに、他のブログを見ると、当社がコンセプトに掲げてある事、8ヶ月かけて14kg体重減をしたこと、脂肪燃焼のプロセスやメカニズムの説明、朝食をバターコーヒーに置き換えた経緯など、私が書いたことをそのままなぞっていると、読んだ瞬間にわかりました(だから、知人もそれに気がついて連絡をくれたと思います。)
周りの人間にも、見せると、「ああ、これはアカンやつやね。これで、社長なん?」と、同意見。「これ、ただの ”サル真似” やん」という知人の言葉には、思わず膝を打ちました。
◆ 真似をする、とは。
「真似」という言葉。ネガティブに捉えられがちですが、実は私たちの多くの学びは真似から始まります。子どもが言葉を覚えるのも、礼節を学ぶのも、すべては真似からのスタートです。スポーツの世界でも、最初は憧れの選手のフォームを真似ることから始まります。つまり、本来の真似は「成長の入口」であり、未来につながる重要な行為です。
しかし、大人になり、自分の軸(実体験/行動)がない状態での真似は、ただの「コピー」や「パクリ」にしかなりません、そう、中身のない「サル真似」です。そこには学びや工夫がなく、浅さだけが際立ちます。今回、私が直面している事例は、まさにその後者に当たります(前職で、中国人/日本人共同オーナーに、3年越しに利益が出だした、事業を横取りされた感覚と同じでした。また、この件の詳細は後日記載します。)
◆ ビジネスの現場で起きていること
Amazonで商品を販売していると、真似をされること自体は珍しいことではありません。ある程度は「仕方がない」と思っています。しかし、問題はそのやり方です。Own Media 論( https://shiftpoint.jp/blogs/entry/2025-0805 )でもお伝えした、その件の当該者は常識を超えていました(今も超えてます。)
- 自分の店の商品に寄せられた否定的なレビューを一部改変して、当社の商品レビューに投稿する。
- 一旦購入してすぐにキャンセルしたにもかかわらず「商品に損失があった」と虚偽のレビューを投稿する。
- 当社がコンサルタントとともに考えたキャッチコピーをそのまま流用する。
- 製造過程で自然に生まれた言葉や表現をそっくりコピーする。(「試験検査合格」「芳醇美味」「徹底的に」初め、ブランドコンセプトなど)
- 挙げ句の果てには、当社が真似をしているとAmazonへクレームを入れ、当社商品を一時販売停止に追い込む。
これらの行動を見れば、誰の目から見ても「自分で考えていない」ことは明らかです。今回、たまたま目にしたブログを見ると、それは突然書き出されたもので、当社のブログからの盗用であることは一目瞭然でした。
まだ、キャッチコピー等の真似なら100歩譲って黙っておきますが、一番許せないのが、実体験/行動が無い状態で、それを顧客に対して情報発信することです。
さらに、顧客はそのような裏事情も知らずに、商品を購入します。この流れが実害を生むので、今回、発信を致しました。
先の Own Media 論( https://shiftpoint.jp/blogs/entry/2025-0805 )でも書きましたが、当社は2回も大きな実害を受けました。
その際の、エビデンス(当該者の名前、会社名、キャンセルしたにも関わらずレビューだけは投稿、それも自分の商品を酷評された内容を少し変えての投稿、他社への同様な行為、当社からアマゾンへの反論文)のスクリーンショットも取ってあります。
さらに、その際、弁護士費用として前金が発生しており、今でも、口座から支払われた金額を見ると、憤りを隠せません。それにも懲りず、まだ、当社の発信する内容だけをなぞり、「サル真似」を続けています。残念ながら、この当該者のような人間は、EC業界には、かなり跋扈しているのが現実です(ご多分にもれず、本人はSNS上ではキラキラした話に終始しています。)
◆ 「真似」と「サル真似」の違い
真似そのものは悪ではありません。むしろ、多くの成功者は「真似ること」から出発し、やがて自分のオリジナルへと進化させています。大切なのは、自分の経験や考えを重ねて「血肉化」できるかどうかです。
一方で、ただ表面をなぞるだけの人は、いつまでたっても借り物の言葉や体験しか語れません。だから文章にも温度がなく、薄っぺらい印象を与えてしまう。読む人は無意識のうちにそれを感じ取ります。浅さは必ず伝わるのです。
私の胸には術後、今でも6本のワイヤーが入っております。それは一生外れることはありません。だからこそ、命をかけた経験から生まれたSHIFTPOiNTの製品は、単なる言葉のコピーでは決して再現できないのです。
そして、このような痛い思いを他の方には絶対に経験してもらいたく無い、じゃ、どうしたらストレス無く無理なく、健康体を維持できるのか? という強い想いから「京都スタイル カビなしコーヒー」が生まれ、毎日口に入れる物にこだわりました。
※ このレントゲン写真は、現在の私の体内です。

◆ 真似をする人の心理
なぜ人はそこまで露骨に真似をするのか。私が思うに、それは「空っぽ」であることの裏返しだと思います。自分の経験や思想がないから、他人の言葉で埋めるしかない。自分の物語を持たないから、借り物の言葉で自分を飾るしかない。
一時的にはうまくごまかせるかもしれません。しかし、見ている人は必ず見ています。そして、借り物の言葉は時間が経つほど「浅さ」として露呈します。本物と偽物の差は、時間が証明するのです。
◆ SHIFTPOiNTが守りたいもの
私は SHIFTPOiNT を立ち上げてから、一つ一つの言葉や表現、そして体験談を大切に積み上げてきました。なぜなら、それらは単なるマーケティング文句ではなく、私自身の実体験や信念から生まれたものだからです。
真似は学びの一歩です。しかし、それは借り物ではありません。その言葉には責任を持ち、商品の向こうにいる顧客としっかりと向き合い、自分自身の言葉と行動でその真実性を語らなければなりません。
◆ 私は愛飲者の喉元と腸に思いを馳る
何度も申しますが、真似をすることは、学びの第一歩です。けれど、真似だけで終わってはいけません。自分の軸、自分の声、自分の道を持ってこそ、真似はオリジナルへと変わります。
今回の出来事を通じて強く思ったのは、借り物ではなく、自分の経験を土台に語れる人間でありたいということ。そしてSHIFTPOiNTは、これからも「クリーンな本物の カビなしコーヒー 」とともに、自分たちの言葉で歩んでいきます。
「サル真似」をする人は、自分の物語を持っていません。けれど、私たちは自分の物語を紡ぎ続ける。その違いが、やがて大きな差を生むと私は信じています、毎日愛飲者の喉元と腸を考え続けながら。